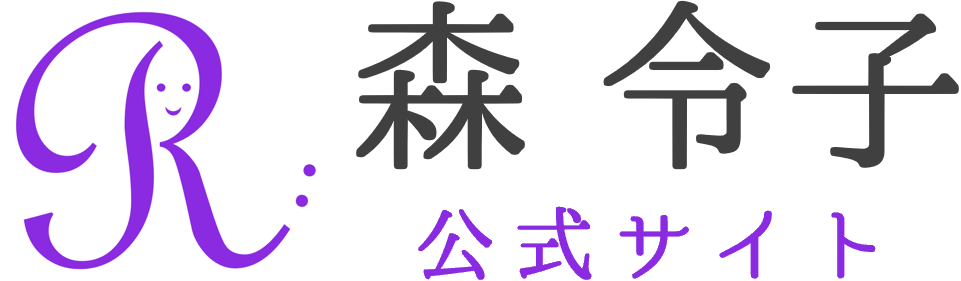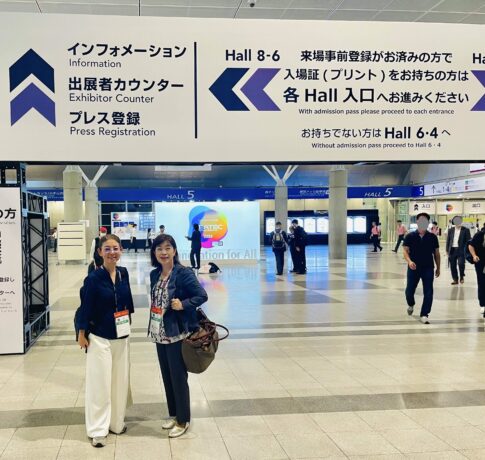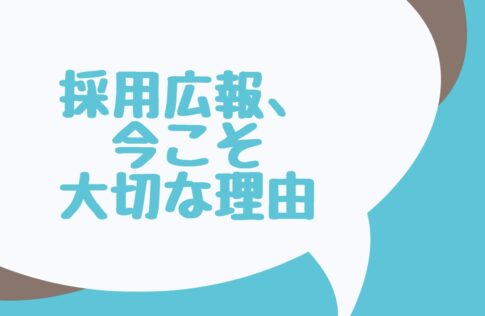カナダのニュースサイトThe Logic コラム(What happens to the news business when people stop clicking?)や、日本経済新聞「生成AIの記事無断利用、著作権法に「隙」 探る最適解」の報道をきっかけに、AI時代のニュースリリースについて実務目線で整理した解説記事を公開しました。
- 本編タイトル:「Google Zero」の衝撃とPRの変革──“AIに拾われる広報”とは
- 公開先:ミライフ ブログ
https://milife1.jp/blog/4094
抜粋(本文より)
「AIに拾われる」とはどういうことか?
公開されたニュースリリースやWeb、資料から、AIが情報を読み取り、要約・再構成し、引用元として紹介するケースが増えています。これは、情報の新たな“読者”としてAIが現れたということです。
AIが好きなのは、どんなニュースリリースか?
AIが引用しやすいコンテンツには膨大な条件があります。そのなかで、ニュースリリース発信において意識できそうな条件には、以下があります。
情報の信頼性 :E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の可視化、専門家の監修コメントや企業代表者の発言・・・・
人に届けるには、事実だけでなくストーリーや共感が大事
現状、生成AIは検証可能な情報を優先して取り込み、回答に反映します。一方で、満足・安心・喜び・などの感情便益は、AIの引用では削ぎ落とされがちです。
こんな方に
- ニュースリリースの構造(出典・時系列・数値・責任所在)を整えたい
- 一次情報+短い物語の両立で、AIにも人にも伝わる発信を目指したい
- 記者・顧客・取引先・採用候補者…多様な読者を前提にしたPR設計を掴みたい
全文はこちら:https://milife1.jp/blog/4094